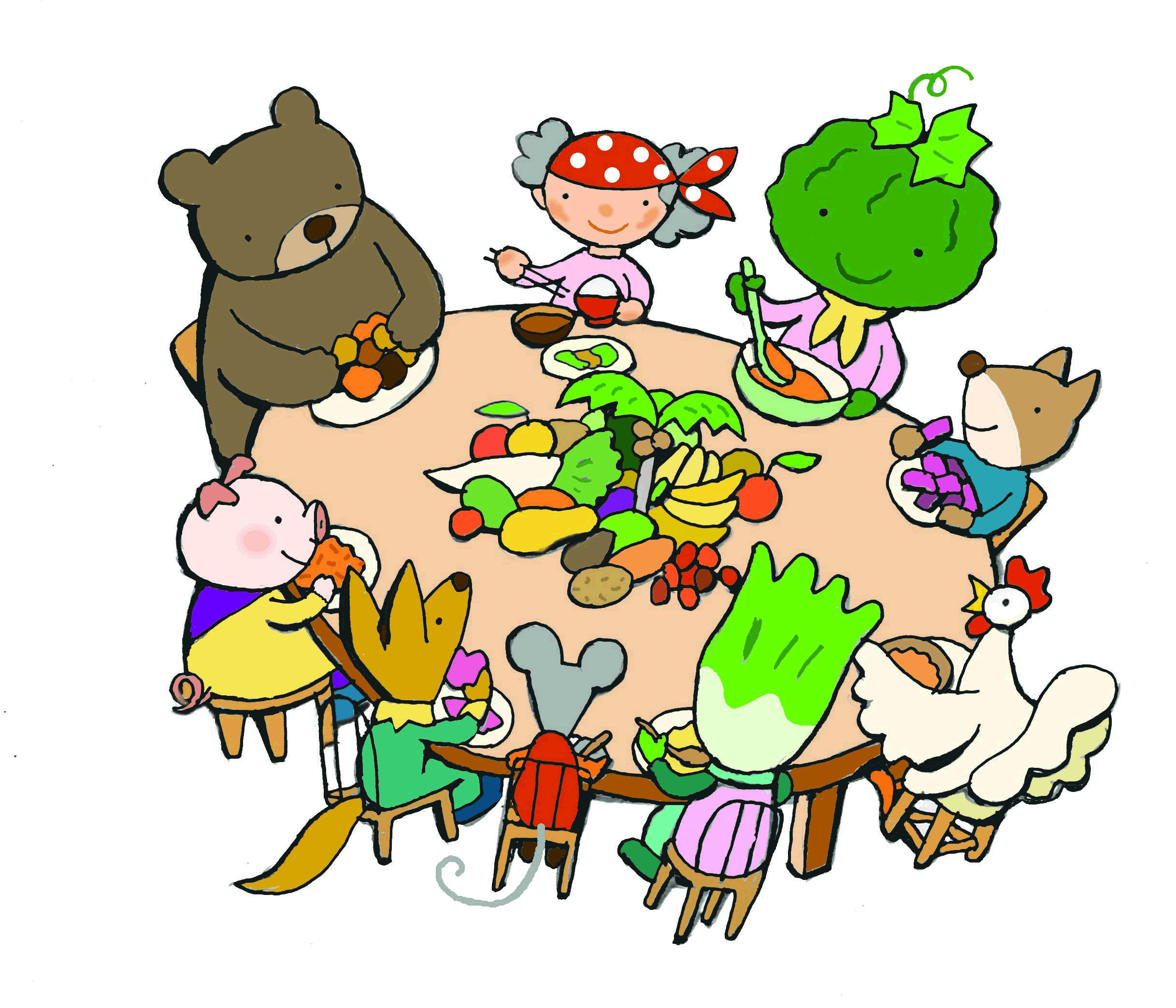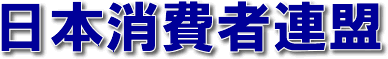昨年2月に主要農作物種子法(以下、種子法)が廃止されて以来、種子を巡る論議がとても盛んです。種子法廃止は農や食のあり方に関わる大事な問題で、論議が巻き起こること自体はとても喜ばしいことなのですが、いくつかの点で違和感も覚えています。
種を巡っては、これまで多くの個人やグループが伝統種の採取や保存に取り組み、現実の農業生産に貢献するなど成果をあげています。ところが今盛り上がっている種子を巡る言説に、そうした人たちの地道な積み上げはほとんど反映されていない、あるいは無視されている感が否めません。
地道な積み上げに代わって幅を利かせているのは、種子がなくなるとたちまち巨大資本(具体的にはモンサント)に種が奪われ、食料主権がなくなる、大変だ、とあおり立てる言説です。そうした側面があることはその通りですが、種とは人がこの地球上で自然とともに生きてきた歩みを凝縮したものです。人と風土(地域)を抜きにして種を制度論あるいは経済論のみで語ることは、種論議をやせ細ったものにしてしまいます。
種とは何かという本源的なところに立ち返って、そこから問題をとらえ返さない限り、種を人々の手に取り戻す運動にはならない。これは秩父という山間地に住み、農のくらしを守り続けてきた人を訪ねて、その地の山と水と土、そこでつくられ伝えられてきたいくつもの種、そこから生まれた食文化の話を聞き歩き、自分でも試してきたことの結論です。
(大野和興)