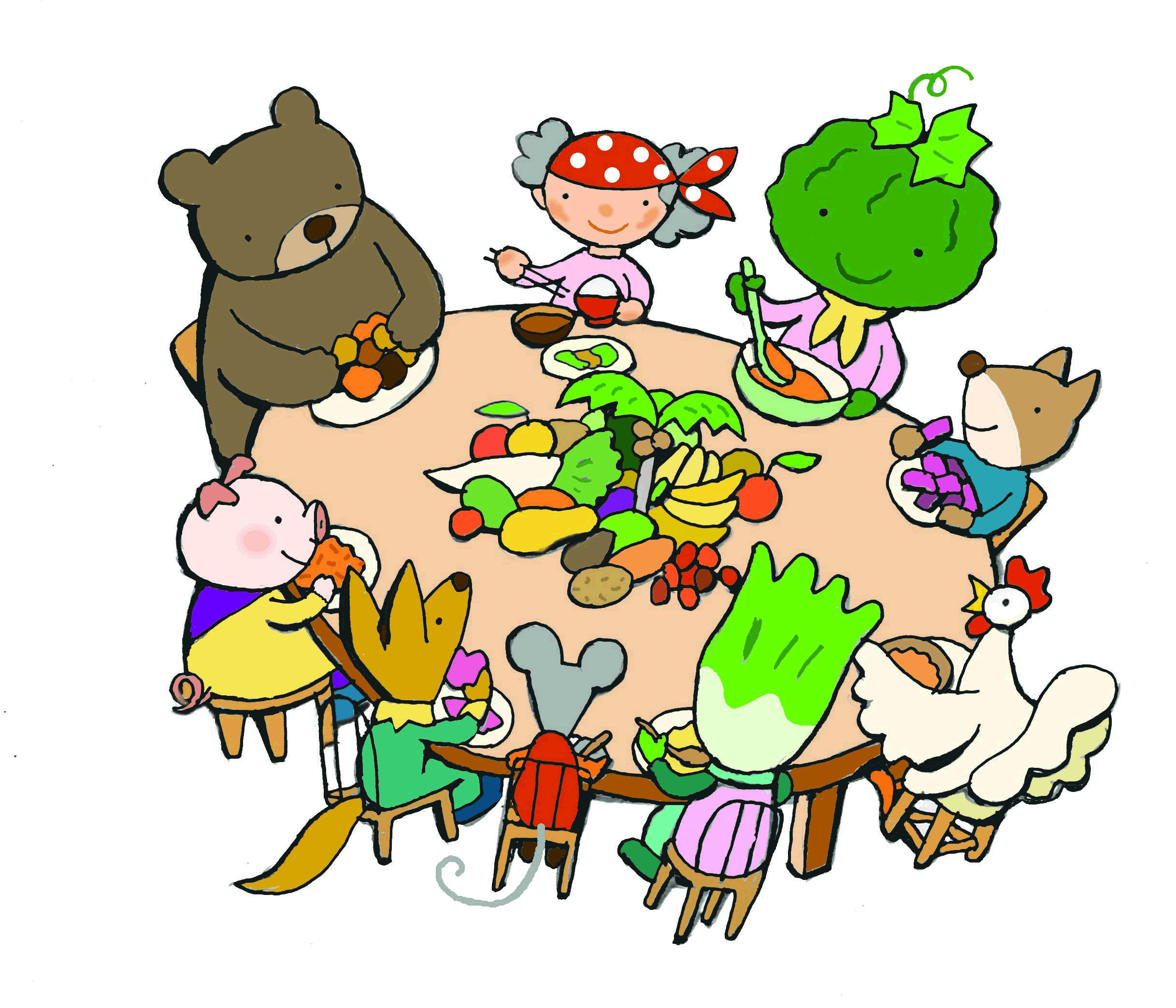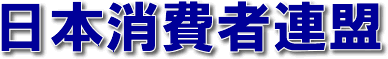日本消費者連盟では、参議院選挙に当たって、各党に質問状を送りましたが、各党からその回答がありましたので、以下に掲載いたします。投票の参考にしていただければ幸いです。
| (質問1)日本では遺伝子組み換え食品に続いて、新たな遺伝子操作技術でつくられたゲノム編集食品が出回っています。政府は、ゲノム編集技術は自然界の突然変異と区別がつかず、科学的な確認ができないとしてゲノム編集表示の義務化は難しいと言っていますが、トレーサビリティなど社会的検証によって表示は可能です。いま全国各地の地方議会からゲノム編集表示の義務化やゲノム編集食品に関する適切な表示を求める意見書が国に対して相次いで提出されています。表示は消費者の知る権利・選ぶ権利を保障するものです。消費者基本法も消費者の権利の尊重を基本理念に掲げています。ゲノム編集表示の義務化についてどうお考えですか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき ②ゲノム編集の表示は義務付ける必要はない ③その他 |
| 自由民主党 | ③その他 ゲノム編集食品は専門家の確認を経て安全性が確保されています。現時点では科学的・社会的検証が難しく、表示義務化は困難ですが、事業者による情報提供の促進が重要だと考えます。 |
| 立憲民主党 | ③その他(消費者が自ら安心・安全を選択できる食品表示制度となるよう見直しを進める) ゲノム編集食品など、論議のある新しい技術を用いた食品等については、予防的見地とともに、消費者が安心して食品を選択することができるようにする観点から、食品表示制度を見直します。 |
| 公明党 | ③その他 ゲノム編集食品の表示については、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかの判別がつかず、表示監視における科学的な検証が困難であることなどの課題があることから、現時点では罰則の伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えますが、今後の技術進展や社会動向等を踏まえて、情報提供や表示の在り方について、必要な検討を行うべきと考えます 一方で、国に届出され、市場に流通しているものについては、事業者が、ゲノム編集技術を利用したことについて、積極的に、消費者に対し、情報提供に取り組むべきです。 消費者が正確な情報に基づき正しい選択を行うためには、制度についての理解は不可欠であることから、引き続き消費者等への周知・普及に努めていく必要があると考えています。 |
| 日本維新の会 | ③その他(いずれでもない) ゲノム編集商品の生産・流通には、正確な情報を消費者に提供し、安心・安全を確保する情報公開が必要です。表示の信頼性を保ち、事業者に過度な負担をかけない合理的な表示制度の設計と、その改善を常に検討することが重要です。 |
| 日本共産党 | ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき 食の安全や生態系への影響など懸念も指摘されており、実用化にあたっては、「予防原則」の立場から遺伝子組み換え食品と同等の規制が必要だと考えます。消費者がゲノム編集食品と認識し、自ら消費を選択できるよう、表示の義務化も必要と考えます。 |
| 国民民主党 | ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
| 社会民主党 | ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき 消費者の知る権利は、消費者基本法、食品表示法に明示されています。ゲノム編集食品を含め全ての遺伝子操作食品の原料表示の義務化、それを担保するトレーサビリティ制度の確立が必要だと思います。 |
| れいわ新選組 | ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき れいわ新選組は、すべての人が「自分の口に入るものを自分で選ぶ」ことができる社会の実現をめざしています。ゲノム編集食品においても、その安全性に対する科学的な不確実性がある中で、消費者の知る権利・選ぶ権利を守るためには、表示義務は当然です。特にトレーサビリティや社会的検証を通じて可能な限りの情報開示を進め、意図しない摂取が生じない制度設計を行う必要があります。 |
| 参政党 | ①ゲノム編集食品にも表示義務を課すべき 消費者の知る権利・選ぶ権利の保障に賛同します |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問2)原料原産地表示は輸入食品を除く全加工食品に義務付けられています。ところが、パンや麺類など小麦を原料とする多くの食品には「小麦粉(国内製造)」と表示されており、これを国産小麦だと誤解している消費者も少なくありません。消費者からは「小麦粉(国内製造)」といった製造地表示を廃止して、生鮮原料の生産地を表示してほしいという声が上がっています。製造地表示についてどのようにお考えですか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①製造地表示は廃止し、生鮮原料に遡った原料原産地表示とすべき ②事業者の実行可能性を考慮し、現行制度を維持すべき ③その他 |
| 自由民主党 | ③その他 全加工食品における原料原産地表示は消費者の意向を踏まえ推進しており、表示の実効性と事業者の負担の両立が必要です。現行制度の下で分かりやすさの向上を図るべきです。 |
| 立憲民主党 | ③その他(消費者が自ら安心・安全を選択できる食品表示制度となるよう見直しを進める) 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、加工食品の分かりやすい原料原産地表示の在り方を検討するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換えやゲノム編集食品、アレルギー表示など、消費者が自ら安心・安全を選択できる食品表示制度となるよう見直しを進めます。 |
| 公明党 | ③その他 加工食品の原料原産地表示制度については、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合であっても、原材料のうち、最も重量割合が大きい生鮮原材料の原産地が確認できる場合には、製造地表示に代えて、その生鮮原材料の原産国の表示を可能としています。こうした仕組みを通じて、事業者が、消費者に対し、分かりやすく信頼できる情報を提供することが重要です。一方で、原料調達先の切り替えに伴う事業者の実務負担にも配慮する必要があります。消費者・事業者双方の状況等を勘案しつつ、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じて、制度の在り方について検討を進めることが重要であると考えます。 |
| 日本維新の会 | ③その他(製造地表示を明記すべき) 原料原産地表示は輸入食品を除く全加工食品に義務付けられているから。 |
| 日本共産党 | ①製造地表示は廃止し、生鮮原料に遡った原料原産地表示とすべき アレルギー物質、残留農薬などのリスク回避のみならず、「国産品を選択し、国内農漁業を応援したい」など、社会的・政治的・思想的・宗教的意図による選択も可能となるよう、消費者の知る権利・消費者の自主的な選択権を保障するべきと考えます。そのため、可能な限り詳細な原料原産地表示を行うべきです。 |
| 国民民主党 | ③その他 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
| 社会民主党 | ①製造地表示は廃止し、生鮮原料に遡った原料原産地表示とすべき 原料原産地表示の厳格化などで消費者の知る権利を保障すべきです。 |
| れいわ新選組 | ①製造地表示は廃止し、生鮮原料に遡った原料原産地表示とすべき 「小麦粉(国内製造)」という表示は、実際には輸入小麦を国内で製粉したものであるにも関わらず、多くの消費者に誤認を与えています。これは、食品表示制度の根幹である「正確な情報提供」に反します。れいわ新選組は、真に消費者の立場に立ち、生産地が明示される制度への改正を求めます。 |
| 参政党 | ①製造地表示は廃止し、生鮮原料に遡った原料原産地表示とすべき 消費者の立場に立った、より正確で判り易い情報提供が必要と考えます |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問3)近年ネオニコチノイド系殺虫剤やその他の浸透性殺虫剤、発がん性のある除草剤グリホサートの使用が増えています。最近はPFAS(超低分解性の有機フッ素化合物)に相当する農薬も多くなっています。これらの中には低濃度で発達神経毒性などを示すものがあり、健康への影響が懸念されます。EUでは予防原則に基づきこれらの農薬の規制が進んでいますが、日本は緩い規制が維持されています。日本の農薬規制についてどのようにお考えですか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①予防原則に従って、農薬規制を強化すべき ②現行規制を維持すべき ③その他 |
| 自由民主党 | ③その他 農薬取締法に基づき、動植物への影響を科学的に評価し、基準を設定します。リスク評価の拡充を通じ、安全確保に努めています。 |
| 立憲民主党 | ③その他(総合的な化学物質対策を進めます) 縦割り行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。 |
| 公明党 | ③その他 現行の農薬取締法に基づく農薬の再評価制度は、全ての農薬を定期的に最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行うとともに、再評価の結果、安全性等が確認できなければ使用基準の変更や登録の取消しも行われることとされており、農薬のリスク管理・規制が強化されたものと認識しています。一方で、国際基準や新たなリスクへの対応を踏まえ、再評価プロセスの透明性・迅速性の向上など、再評価制度の運用については不断の見直しが必要と考えます。 |
| 日本維新の会 | ③その他(科学的知見に基づいた安全確保のための規制と合理的な食糧増産を両立すべき) |
| 日本共産党 | ①予防原則に従って、農薬規制を強化すべき 日本は予防原則を採用しておらず、新たに指摘された弊害への科学的な機序が明確に証明されない限り規制がされない傾向があります。そのため研究機関や国際機関においてリスクが報告されても大規模なコホート研究などが行われません。農薬の身体・環境への影響を継続的に見直し、必要に応じて規制を強化していく仕組みが不十分です。農薬取締法改正(2018 年)に伴って農薬再評価を開始しましたが、科学情報を提供する公表文献を収集・選択する主体が審査を受ける当事者である農薬企業が行うというお手盛りの運用がなされています。予防原則に基づいた客観的・再帰的で厳格な規制制度が必要と考えます。 |
| 国民民主党 | ③その他 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
| 社会民主党 | ①予防原則に従って、農薬規制を強化すべき 健康被害が発生してからの規制では消費者の健康と安全を守れません。EUと同等レベルの予防原則に基づく農薬規制を強化するべきです。 |
| れいわ新選組 | ①予防原則に従って、農薬規制を強化すべき 人体や生態系への長期的な影響が不明な農薬については、使用を制限・見直すべきです。特にネオニコチノイド系農薬やグリホサート、PFASに類する新しい農薬に対しては、EUと同様、予防原則に基づいた強化された規制を速やかに導入し、安全・持続可能な農業への転換を支援するべきです。 |
| 参政党 | ①予防原則に従って、農薬規制を強化すべき 諸外国でも規制されているものについては、より慎重に扱うべきと考えます |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問4)米国トランプ政権の追加関税を巡る日米交渉で、米国産のコメや大豆、トウモロコシなどの農産物の輸入を拡大したり、牛肉やジャガイモなどの検疫の緩和などを行おうとする動きがあります。これらの動きについてどうお考えですか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない ②交渉の妥結のためならば一定の譲歩をするのもやむを得ない ③交渉の妥結のためならば一定の譲歩もやむを得ないが、コメは輸入すべきでない ④国内のコメ価格高騰解消のためにコメの輸入拡大をするべきである ⑤その他 |
| 自由民主党 | ③ 交渉の妥結のためならば一定の譲歩もやむを得ないが、コメは輸入すべきでない 食料安全保障と国内農業を守る観点から、コメの輸入拡大には慎重であるべきです。一方で国際交渉では柔軟な対応も必要です。 |
| 立憲民主党 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない |
| 公明党 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない 米国の関税措置に関する日米交渉においては、日本は米国からとうもろこし、大豆、小麦、牛肉など多くの農畜産物を輸入し、米国側が約2兆円の貿易黒字であることから、米国の農業者、食品産業に多大な貢献を行っていることを強く主張していくべきです。加えて、これまでの日米貿易協定の交渉等を通じてできる限りの市場アクセス改善を行っており、拙速な交渉は断じて行うべきではないと考えています。 |
| 日本維新の会 | ②交渉の妥結のためならば一定の譲歩をするのもやむを得ない 交渉のカードは幅広く持つべきだが、国内農業への影響は可能な限り抑えるべき。 |
| 日本共産党 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない トランプ大統領が米国への輸入品に一方的に関税を課すことは、これまで米国自身が主導してきた貿易ルールにも反し、他国民の犠牲をいとわない身勝手なやり方です。毅然として撤回を求め、日本経済や暮らしへの悪影響を防ぐ万全の対策を取るべきであり、農作物の輸入拡大・規制緩和を交渉のカードとすること自体、言語道断だと考えます。 |
| 国民民主党 | ⑤その他 まず交渉内容について最低限の情報公開と共有を求めます。同時に、トランプショックによる経済への影響を勘案し、内需の拡大、そのための減税政策、手取りを増やす政策を実現しなければなりません。米国に対しては、与野党を超えて日本がOneチームで交渉に臨み、両国にとってお互いの国益となる関税交渉としていくことが重要です。 ※回答時の見解であり、交渉状況等によって修正・変更することがあることに留意ください。 |
| 社会民主党 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない 中長期的な食の安全確保、輸入農産物の検疫基準を厳格化し、食品の安全を確保するべきです。 |
| れいわ新選組 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない 日本の食料主権を守るためには、国内農業を基盤とした自給体制の強化が不可欠です。農薬基準や遺伝子組み換え規制の緩い輸入農産物の拡大は、国民の健康と国内農家の経営を脅かします。れいわ新選組は、これに強く反対します。 |
| 参政党 | ①農産物の輸入拡大や検疫緩和を行うべきではない 食料安全保障は最優先で護るべき。アメリカの誤った関税率の理解を正す必要がある |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問5)農業の担い手不足や耕作放棄地問題が深刻になる中で、日本においても欧米並みの「農家への所得補償(直接支払い)」を行うよう求める意見が高まっています。これらの動きについてどうお考えですか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである ②所得補償は農業の規模拡大などにつながらないので導入すべきでない ③条件不利地域対策や環境保全型生産への補助など現在の「日本型直接支払い」制度を拡充すべきである ④その他 |
| 自由民主党 | ④その他 農業者の所得補償については、ただ単に一律に所得を補填するのではなく、農業の収益性や構造改革と一体となった形での支援が重要だと考えています。 |
| 立憲民主党 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである 食料安全保障の確立は、喫緊の課題であると考えています。まずは食料自給率50%を目指すために、かつて実施された農業者戸別所得補償制度を礎(いしずえ)に、消費者・国民へ農産物を安定的に供給する基礎となる農地を維持するため、農地に着目した新たな直接支払制度「食料確保・農地維持支払(食農支払)」を創設します。 |
| 公明党 | ④その他 価格下落時や不作時など生産者の経営リスクを支えるため、セーフティネット対策を強化する必要があると考えます。 その上で、生産者の再生産可能な所得を確保するためには、地域や営農方法も踏まえて検討すべきであり、現行の日本型直接支払い制度の拡充や収入保険の拡充など、令和9年度に予定される水田政策の見直しに向けた議論の中で、与野党の垣根を超えた幅広い議論を行う必要があると考えます。 |
| 日本維新の会 | ④その他 自然災害や価格変動に対応するセーフティネットを強化し、中山間地を含む農家の経営安定化を支援します。 |
| 日本共産党 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである 農業の担い手不足や耕作放棄地の解消には、農業者が意欲をもって生産に励み、農村で暮らし続けられる条件を政治の責任で整えることが不可欠です。そのために必要なのは、主な農産物の再生産を可能にする価格保障と所得補償が必要です。条件不利地の維持、国土や環境の保全など多面的機能に配慮することが求められます。 |
| 国民民主党 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである 食料安全保障の強化のためには、国内の生産力を高める必要があり、「営農継続可能な農業者の所得向上」が不可欠です。適正な価格形成に向けた環境整備を消費者の理解を得ながら進めるとともに、「食料安全保障基礎支払」(稲作:15,000円/10a、畑作・果樹等:10,000円/10a、含「洪水防止機能加算」)を創設するほか、中山間地域等直接支払制度の拡充や、「多面的機能支払」(農業生産による外部経済効果に対する支払)の導入により、直接支払い制度を再構築します。 |
| 社会民主党 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである 農業者戸別所得補償制度を復活させ法制化・恒久化する必要があります。また新規就農者を含め農業者への支援策をさらに拡充するべきです。 |
| れいわ新選組 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである 農業は国の命綱です。欧米に倣い、農業の持続可能性を確保するために、価格保証や直接支払いなどの所得補償制度を導入し、特に中山間地の小規模農家にも支援が届く制度を構築すべきです。農業政策予算の抜本的増額も必要です。 |
| 参政党 | ①農家が安定的な生産ができるよう「所得補償政策」を導入すべきである G7はじめ諸外国では直接所得補償を行っている国々も多くみられる。参政党では農家の準公務員化までを視野に入れた政策提言を行っている |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問6)「学校給食の無償化」にむけた法案が検討されていますが、その一方で、無償化に伴い、各自治体の独自の取り組みが縮小され給食の「質」が低下するという懸念も出されています。特に有機食材を使った給食の推進のためにどのような政策が必要だと思いますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。 ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ ②有機給食の食材分については自治体が独自に負担すべきだ ③有機給食の支援は必要ない ④その他 |
| 自由民主党 | ④その他 国として、学校給食における有機食材の活用は重要と考えておりますが、学校給食における有機食材の導入、その無償化については、各自治体において、地域の実情に応じてご判断いただくことが適切と考えております。 |
| 立憲民主党 | ④その他 公立小中学校の給食を無償化しつつ、質の担保を図ります。食を通じて、健康な身体や心を培い、食と農に対する理解を深める「食育」を進めます。また、朝食の取れない児童・生徒に対する朝給食の導入、学校給食の無償化・オーガニック化、子ども食堂などの取り組みを支援します。有機農業に取り組む農業者を支援し、指導者を育成・確保するとともに、学校給食等への利用を推進し、有機農産物の市場を拡大します。 |
| 公明党 | ④その他 学校給食については、こども家庭庁、農林水産省、文部科学省等が連携して無償化を進め、主食・おかず・ミルクのそろった完全給食の実施、食育の充実、地産地消の給食や有機野菜を使った給食を推進します。自民党・公明党・日本維新の会が3党で合意した文章には「地産地消の推進を含む給食の質の向上、国と地方の関係、効果検証といった論点について、十分な検討を行う」とあり、今後、有機給食も含めて検討していきます。 |
| 日本維新の会 | ④その他(有機給食は自治体が独自に進めるべきだが、無償化は推奨すべき) 学校給食は無償化を推進しています。有機給食については各自治体に委ねています。 |
| 日本共産党 | ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ 有機食材を学校給食に採用することは、みどり戦略の策定時から有機農業関連の団体がそろって中心課題として要求してきた点であり、国の制度と対応が不十分だと考えています。現在のところ、「みどりの食料システム戦略推進交付金」のうちオーガニックビレッジ創出事業の一環として交付されるものでしかなく、予算総額もそれ以外の事業と合わせてわずか3億6100万円ほどと、あまりに小さく、有機食材の給食に採用するためのかかり増しを国が直接負担するような、強いインセンティブを設定するべきです。日本共産党は、長年にわたり国や自治体に対して学校給食の無償化を求め、全国で要求運動を推進してきました。多くの自治体が「食材費は保護者負担」と規定している学校給食法を盾に、給食無償化を拒んできましたが、吉良よし子参議院議員の度重なる要求に対して国がようやく「学校給食法は給食費の一部補助を禁止していない」と答弁したことにより、自治体が無償化を進めない根拠が崩れ、運動が一気に全国に拡大しました。今後はさらに、自治体の財政力の違いで子どもたちの給食の質が左右されないようにするため、「地方創生臨時交付金を活用しろ」というのではなく、国が給食無償化の費用を一律に財政負担する仕組みを整えるべきと考えます。 |
| 国民民主党 | ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ 小中学校の学校給食を早期に無償化します。 食材は農産物、水産物ともにできるだけ地産地消のものとし、併せて有機農産物の利用を推進、国産化・食育活動の推進を進めます。遺伝子組み換え食品も学校給食では使いません |
| 社会民主党 | ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ 学校給食は子どもの成長発達に大きく影響します。自治体レベルで給食の無償化が進んでいますが、自治体間で格差があってはなりません。まずは自治体間の格差是正のために、有機農業推進とセットで、国による学校給食の全面無償化を実現していきます。 |
| れいわ新選組 | ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ 国全体で子どもを育むという理念のもと、れいわ新選組は、全ての自治体で18歳までの子ども医療費や、学校給食費、保育料、学費、小学校の放課後対策事業(学童)の費用をすべて無償化(5つの無償化)すべきと訴えています。財源については、地方自治体に押し付けるのではなく。国が責任を持って保障すべきです。 その際、学校給食の食材は可能な限り有機農産物によることとし、自治体に対しその財源を給付し、都市部と生産地とのマッチングを図るなどにより自治体の給食の有機化を支援します。食育の観点からも、地元の有機食材の利用がきわめて重要です。 |
| 参政党 | ①有機給食の食材分もあわせて無償化を国の負担で進めるべきだ 給食の量や質を低下させかねない現在の給食無償化方針には反対しています |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問7)政府は2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓から決定された「原子力発電は可能な限り低減する」との方針を転換し、原発再稼働や新増設を進めています。原発政策について、どう考えますか。以下から1つを選んで、その理由をお聞かせください。 ①すべての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす ②既存の原発で安全性を確認し、一部は再稼働を行う ③再稼働に加えて、新増設も実施する ④その他 |
| 自由民主党 | ④その他 原子力規制委員会により厳しい安全性基準への適合が認められた原発については、立地自治体等関係者の理解と協力のもと再稼働を進めます。新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・設置に取り組みます。 |
| 立憲民主党 | ①すべての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす 地域の特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現します。原子力発電所の新設・増設は行わず、全ての原子力発電所の速やかな停止と廃炉決定を目指します。実効性のある避難計画の策定、地元合意がないままの原子力発電所の再稼働は認めません。避難計画については、原子力防災会議の意見、内閣総理大臣・原子力規制委員会の同意を法定し、国の責任を明確化させます。 |
| 公明党 | ②既存の原発で安全性を確認し、一部は再稼働を行う 徹底した省エネや、ペロブスカイト太陽電池や洋上風力など再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取り組みは強化していきます。他方、電力需要の大幅な増加が見込まれている中では、火力発電の低・脱炭素化の加速、原発の抑制的な活用を通じて、エネルギー危機に強い需給構造への転換を進め、低廉で安定したエネルギーを供給することが必要だと考えています。 |
| 日本維新の会 | ③再稼働に加えて、新増設も実施する 原発再稼働にあたっては、各立地地域に地域情報委員会を設置し、住民との対話と合意形成の場をつくり、理解促進を図るとともに、発電所の内部脅威に対し、国の責任で個人の適格性審査確認制度(セキュリティクリアランス)を設け、安心できる運営体制を確保します。そのうえで、わが国の原子力人材の確保を図るためにも、米国と共同研究している小型原子炉(SMR)や、有毒性を低減する高速炉など、安全性の高い次世代型原子炉の実用化に向けて研究開発に取り組みます。 |
| 日本共産党 | ①すべての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす 福島原発事故の被害は甚大で、住民の暮らし、生業、文化など地域社会を壊しました。原発が抱えるこのような危険性は、社会的に受け入れ難いものです。2013年から15年にかけて稼働原発ゼロでした。電力需給の面からみても原発は不要です。すみやかに原発ゼロとすべきです。 |
| 国民民主党 | ③再稼働に加えて、新増設も実施する 原子力発電所の再稼働・リプレース・新増設や核融合等で安価で安定的な電力確保とエネルギー自給率50%を実現します。高効率火力発電によるカーボンニユートラルを推進します。 |
| 社会民主党 | ①すべての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす 震大国日本で原発の稼働は不可能です。社民党は原発を即時停止し、原発並びに原子力関連施設の廃止に向けた「原発ゼロ基本法案」を早期に成立させ、具体的なロードマップを作成していきます。 |
| れいわ新選組 | ④その他(原発は即時禁止することで停止し、電力会社から資産を買い取り、廃炉・解体を順次進めていく) れいわ新選組は「脱原発・廃炉ニューディールで全国に安心を!地域に未来を!被害者に賠償を!」をスローガンに、以下の3つの政策を掲げています。(1)原発は即時禁止!政府が買い上げて廃炉を進めてゆく。(2)原発立地地域の「公正な移行」のための「廃炉ニューディール」を!(3)福島第一原発事故の被害者をだれも取り残さない。 |
| 参政党 | ②既存の原発で安全性を確認し、一部は再稼働を行う 喫緊の安定したエネルギー確保には必要だが、将来的にはより安全で環境負荷の少ない新型原子力発電への置き換えを進めるべき |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問8)政府は第7次エネルギー基本計画を決定し、原発を持続的に利用する方針を掲げて、2040年度の電源構成を再生可能エネルギー40%~50%、原子力を20%、火力を30%~40%としました。将来のエネルギーのあり方について、どう考えますか。以下から1つを選んで、その理由をお聞かせください。 ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう ②エネルギー基本計画のとおりでよい ③その他 |
| 自由民主党 | ②エネルギー基本計画のとおりでよい 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの最大限の導入、徹底した省エネルギー、原子力の最大限活用を柱に、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指します。 |
| 立憲民主党 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 気候危機対策を強力に推進し、2030年の再生可能エネルギーによる発電割合50%及び2050年100%を目指し、2050年までのできる限り早い時期に化石燃料にも原子力発電にも依存しないカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)達成を目指します。 |
| 公明党 | ②エネルギー基本計画のとおりでよい 脱炭素電源の最大限活用が急務となる一方で、これまで減少傾向だった電力需要が増大する傾向に転じるとともに、不確実性がより顕著になるなど前提条件が大きく変化しています。第7次エネルギー基本計画は、特定の電源や燃料源に過度に依存しないバランスのとれた電源構成をめざしており、エネルギー自給率の向上、S+3E(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合)の原則を踏まえ、2040年のエネルギーミックスや複数のシナリオも考察しながら構成されていると認識しています。 |
| 日本維新の会 | ③その他 太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入を進め、規制見直しや地域経済の活性化を図る仕組み作りを行います。 |
| 日本共産党 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 再生可能エネルギー100%をめざすことは、気候危機打開のためにも、持続可能な社会のためにも不可欠です。脱化石燃料を展望して、2030年度までに石炭火力発電を廃止すること、省エネルギーと再エネ利用の拡大をすすめることが必要です。再エネ拡大の障害となっている原発はすみやかにゼロにすべきです。 |
| 国民民主党 | ③その他 S+3Eを大前提に、共生・自立・分散型のエネルギーネットワークを構築し、他国依存度の低い電源(再生可能エネルギーや小型モジュール炉(SMR)等)を中心としたマイクログリッドを含む自立・分散型エネルギー社会の構築をめざします。特に洋上風力、地熱の活用に注力するとともに、ジオエンジニアリングに取り組みます。地熱・中小水力・バイオマス・太陽光・風力等の各地域資源の有効活用や電源立地地域への産業集積等を通じて地方の可能性を引き出します。再エネ賦課金が増大し国民に大きな負担となっていることから、再エネ賦課金制度のあり方を検証し必要な見直しを行います。2030年代には電源構成比で再エネ比率が40%以上となるよう自治体等の関係者の合意を得つつ着実な取り組みを進めます。 |
| 社会民主党 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 第7次エネルギー基本計画では「可能な限り原発依存度を低減」という文言を削除し、原子力を再生可能エネルギーと共に「最大限活用」することとし、さらには原発の建て替えを促進する原発回帰の内容です。国の政策がもたらした福島第一原発事故の反省と教訓を忘却する愚行です。基本計画を撤廃するべきです。また、再生可能エネルギーをエネルギー政策の本流に位置づけ、導入促進に全力をあげるべきです。社民党は再生可能エネルギー電力目標を「2030年 50%、2050年 100%」としています。再生可能エネルギーの活用は、地域の雇用創出や内需拡大につながり、すそ野の広い経済効果を考えます。 |
| れいわ新選組 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう れいわ新選組は「脱原発と脱炭素を両立させ、日本を自然エネルギー大国に!」をスローガンに、以下の3つの政策を掲げています。(1)2050年までに「自然エネルギー100%」のカーボン・ニュートラルを実現する(2)エネルギー変革のために、10年間で官民あわせて200兆円のグリーン投資を行う~全ての人々に雇用を、すべての地域に富を、新たな技術に資金を!~(3)バッズ課税を、すべての人々の命と暮らしを支える再分配に活用する |
| 参政党 | ③その他 行き過ぎた再エネ推進方針は見直し、国内より環境影響の大きい諸外国の改善に協力する方針に切り替えていくべき。 |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問9)2022年3月の国連環境総会で、プラスチック汚染を終わらせるために法的拘束力のある国際条約をつくることが決まりました。条約の内容を議論する最終会合が2024年11月に韓国で行われましたが合意にいたりませんでした。今年8月にはスイスで合意が目指されています。どのような条約にすべきか、望ましいと考える内容を以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす ⑤拡大生産者責任を明確にする ⑥プラスチックは有用なので、何もする必要はない ⑦その他 |
| 自由民主党 | ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペアの機会を増やす ⑤拡大再生産者責任を明確にする ⑦その他 極端な生産削減ではなく、リサイクル・リユースや生産者責任の強化など、循環型社会の構築を国際条約の柱とすべきです。実効性と実現可能性を両立したルールが必要です。 |
| 立憲民主党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペアの機会を増やす ⑤拡大再生産者責任を明確にする ⑦その他 l3R(リデュース・リユース・リサイクル)の基本として、使い捨てプラスチックの使用量を減らすことが最も必要かつ効果的な対策であることから、脱使い捨てプラスチック社会を目指し、「廃プラゼロ法」の制定を検討します。 lプラスチック汚染に関する法的拘束力ある国際条約の策定に向け、実効的な国際条約となるよう後押しします。 l事業者の使い捨てプラスチック削減の取り組みは限定的であるため、ライフスタイル変革に不十分な現行の政策を見直します。 |
| 公明党 | ⑦その他 リユース、リペアを進めるとともに、廃棄物となったものについてはリサイクルを推進することが重要であると考えます。 |
| 日本維新の会 | ③リサイクルを推し進める 分別や廃棄方法のあり方を適切に見直すなど、処理技術の現状や科学的エビデンスに基づいた対策を進めます。 |
| 日本共産党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ④リサイクルよりリユースやリペアの機会を増やす ⑤拡大再生産者責任を明確にする |
| 国民民主党 | ⑦その他 マイクロプラスチック問題の深刻化を踏まえ、国際的な取り組みを強化するとともに、生態系への影響を防止するための規制を導入します。ペットボトルやプラスチック等のリサイクル・回収制度普及を進めマイクロプラスチック対策を加速化させます。 |
| 社会民主党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ⑤拡大再生産者責任を明確にする |
| れいわ新選組 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ⑤拡大生産者責任を明確にする |
| 参政党 | ③リサイクルを推し進める |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問10)PFAS(有機フッ素化合物)について、米国では法的拘束力のある飲料水中の基準値を、PFOS・PFOAは4ng/L、PFNAやPFHxSなど他の3種類のPFASと、2種類以上のPFASの混合物質については10ng/Lと設定しました。欧州連合では1万種類すべてのPFASを1つのグループとして捉え、原則全面的な製造・販売を禁止する法案を検討中です。一方、日本のPFAS暫定目標値は、PFOSとPFOAが合計で50ng/Lという緩い状態です。今後、日本はどのようにすべきだと考えますか。望ましいと考える内容を以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①基準値をアメリカ並みに厳しく設定する ②欧州連合のように原則全面的に禁止する ③将来的にはPFAS全般を禁止すべき ④今のままでよい ⑤その他 |
| 自由民主党 | ⑤その他 PFOSなどについては、水道水中の管理目標値を設けてモニタリングを強化していきます。また環境中のPFASの低減に向けた技術開発や健康影響に関する新たな知見の発信を進め、住民の不安解消に努めます。 |
| 立憲民主党 | ⑤その他 lPFAS汚染問題は、生きる上で基本となる安全な水の確保の問題です。国民の健康と安全を守る立場として、汚染源特定のためにモニタリングの強化を図るとともに、広く血液検査を行い、PFASの血中濃度が高い場合に相談や支援につながる仕組みを設け、これ以上のPFAS汚染の拡大防止と市民の不安の解消を目指します。 lPFASは多くの製品等に使用されてきたことから、関係する省庁が多く、主導的に取り組む省庁がないことから、省庁間の連絡会議などを設けるとともに、PFAS問題に政府が責任をもって取り組む体制をつくります。 lPFAS等、特定の化学物質等による水の汚染が疑われる場合に、地方自治体のみに任せるのではなく、国が汚染源を特定し、環境・健康調査をすることを義務付け、飲み水の安全を確保する等の法整備を目指します。 |
| 公明党 | ⑤その他 最新の科学的知見に基づき、適切な目標水準を設定する必要があると考えます。 |
| 日本維新の会 | ⑤その他 生態系に与える影響を十分に配慮しつつ、慎重に検討していく必要があると考えます。 |
| 日本共産党 | ①基準値をアメリカ並みに厳しく設定する ②欧州連合のように原則全面的に禁止する |
| 国民民主党 | ⑤その他 人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。 化学物質の製造から廃棄までの全体を予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。 |
| 社会民主党 | ②欧州連合のように原則全面的に禁止する ③将来的にはPFAS全般を禁止すべき |
| れいわ新選組 | ⑤その他(①→②→③の順で段階的に禁止を強めていく。) |
| 参政党 | ①基準値をアメリカ並みに厳しく設定する |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問11)プラスチック削減のため、必要性が低くかつ有害性の高い人工芝のようなプラスチック製品をまずなくす必要があると考えます。例えば、屋外に敷設された人工芝は紫外線の影響で2~4年で著しく劣化し、大気中のマイクロプラスチックにもなることが指摘されています。また、使用後の処理も困難で、多くは埋立地に埋め立てられるか、リサイクルと称し他の場所で防草シートなどとして使用されます。このような製品は、2023年のG7気候・エネルギー・環境大臣会合(札幌)で合意された「2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする」目標にも抵触します。人工芝のマイクロプラスチック対策は不可能であるため規制すべきですが、これについてどう思いますか。以下から1つ選んでください。 ①人工芝を減らすため、国レベルでの規制が必要 ②人工芝もプラスチックも減らす必要はない ③その他 |
| 自由民主党 | ③その他 マイクロプラスチックの影響に関する懸念は理解していますが、現時点では科学的知見が十分でないとされており、まずは環境中での実態把握や生態系・健康への影響評価手法の確立が必要です。 |
| 立憲民主党 | ③その他 党として規制の有無について判断はしていませんが、人工芝からのマイクロプラスチック汚染を含めプラスチック問題について、今後も議論を重ねていきます。 |
| 公明党 | ③その他 人への健康影響などの知見が十分ではないため、科学的知見の充実に努めるべきと考えます。 |
| 日本維新の会 | ③その他 人工芝だけが規制対象とされる理由が不明確です。 |
| 日本共産党 | ①人工芝を減らすため、国レベルでの規制が必要 |
| 国民民主党 | ③その他 マイクロプラスチック問題の深刻化を踏まえ、国際的な取り組みを強化するとともに、生態系への影響を防止するための規制を導入します。ペットボトルやプラスチック等のリサイクル・回収制度普及を進めマイクロプラスチック対策を加速化させます。 |
| 社会民主党 | ①人工芝を減らすため、国レベルでの規制が必要 |
| れいわ新選組 | ①人工芝を減らすため、国レベルでの規制が必要 |
| 参政党 | ①人工芝を減らすため、国レベルでの規制が必要 |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問12)香害による被害の声が、消費生活相談に寄せられ続けているため、2021年から、国の5省庁(消費者庁・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・環境省)は、香りへの配慮を促すポスターを作成し、周知を行っています。しかし、香害は、消費者の使用法の問題ではなく、製品に含まれる化学物質の安全性の問題です。科学的解明を待たずとも、予防原則に基づき、規制を含め、香害を生む製品への国の対応が必要だと思います。この考えに賛成ですか。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①はい ②いいえ ③わからない ④その他 |
| 自由民主党 | ④その他 香りの感じ方は個人差があるため、香害への理解を広げる啓発とともに、科学的知見の収集に努めることが重要だと考えます。 |
| 立憲民主党 | ④その他 縦割り行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。昨今、被害が増加してきた香害などへの対応を含め、成分表示や表記の統一等、化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の検討を進めます。 |
| 公明党 | ④その他 香りへの配慮については、令和3年から、政府において、関係省庁連名で「香りにより困っている方がいることへの理解」や「香りの感じ方には個人差があること」等を周知する啓発ポスターを作成し、自治体等に配布し周知に努めていると承知しています。また、事業者や業界団体においても、香料成分表示などの情報提供や、香りに関する注意喚起を製品の品質表示自主基準に盛り込むなどの取組みを行っているものと認識しています。いわゆる香害を含む化学物質過敏症については、病態や機序に未解明な部分が多く、診断基準も確立していないため、診断基準や治療法の確立に向け、病態や機序の解明のための研究を通じた知見の集積の取組が行われており、現時点でいわゆる香害の観点から製品を規制することは困難と考えておりますが、引き続き、関係省庁や業界とも連携しながら、香りへの配慮等について、対応してまいりたいと考えております。 |
| 日本維新の会 | ④その他 科学的根拠なき規制は香りの好き嫌いの問題との線引きが難しく、まずは科学的根拠をもった基準を策定することが重要と考えます。 |
| 日本共産党 | ①はい |
| 国民民主党 | ④その他 縦割り行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。また、建築物に由来する化学物質被害を防止し、シックハウス被害者がこれ以上増加することを防ぐため、建築物完成後の居室内の有害化学物質濃度測定を義務化し、基準を超えた場合には改善を求める、大規模な公共建築物における有害化学物質の定期的な測定を義務付ける等を内容とするシックハウス対策のための法制度の検討を進めます。 |
| 社会民主党 | ①はい |
| れいわ新選組 | ①はい |
| 参政党 | ①はい |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問13)日用品やパーソナルケア製品から揮発する香料や消臭抗菌成分などの化学物質が充満することで、公共施設の利用や、集まりへの参加の機会を奪われている人々が存在します。退職、失業、不登校となる事例も多数です。この現状は、共生社会実現を目指している障害者差別解消法の趣旨に反します。厚生労働省の研究班でも、「生活衛生上、香料の使用は十分に考慮される必要がある」との考えを示しています。共生社会の実現を目指すために、学校、医療機関、公共施設などでの空気のバリアフリー化が必要だと思います。この考えに賛成ですか。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①はい ②いいえ ③わからない ④その他 |
| 自由民主党 | ④その他 公共施設における対応は、障害者や高感受性者への合理的配慮の範囲で個別に検討すべきであり、全国一律の「空気の規制」は科学的妥当性を欠く可能性があります。 |
| 立憲民主党 | ④その他 これまで党で検討できていませんが、議論していきたいと考えます。 |
| 公明党 | ④その他 柔軟剤等の香料として使用される微量な化学物質に接することにより、頭痛やめまい等の多様な症状を訴える方がいらっしゃるものと認識しております。香りでお困りの方々がいることは事実であり、令和3年から、政府において、関係省庁連名で「香りにより困っている方がいることへの理解」や「香りの感じ方には個人差があること」等を周知するポスターを作成し、自治体等に配布し周知に努めていると承知しています。一方、いわゆる「香害」を含む「化学物質過敏症」の病態や機序には未解明な部分が多く、疾患概念や診断基準も確立していないため、現時点では一律な規制を行うことは困難であると考えておりますが、引き続き、関係省庁や業界とも連携しながら、香りへの配慮等について、対応してまいりたいと考えております。 |
| 日本維新の会 | ④その他 空気のバリアフリー化についても、どの程度の水準が妥当なのか複数の見地からの科学的な調査と研究が必要と考えます。 |
| 日本共産党 | ①はい |
| 国民民主党 | ④その他 縦割り行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。また、建築物に由来する化学物質被害を防止し、シックハウス被害者がこれ以上増加することを防ぐため、建築物完成後の居室内の有害化学物質濃度測定を義務化し、基準を超えた場合には改善を求める、大規模な公共建築物における有害化学物質の定期的な測定を義務付ける等を内容とするシックハウス対策のための法制度の検討を進めます。 |
| 社会民主党 | ①はい |
| れいわ新選組 | ①はい |
| 参政党 | ③わからない |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問14)化学物質・化学品の危険有害性を示す、世界共通のGHS表示を洗剤・柔軟剤等の家庭用品にも行うべきだと思いますか。 ①はい ②いいえ ③わからない ④その他 |
| 自由民主党 | ②いいえ 家庭用品にまで国際的なGHS表示の義務を拡大することは、過剰表示による混乱や事業者負担の増大を招く懸念があり、段階的・合理的な対応が求められます。 |
| 立憲民主党 | ④その他 これまで党で検討できていませんが、議論していきたいと考えます。 |
| 公明党 | ④その他 洗剤や柔軟剤等の香料として使用される微量な化学物質に接することにより、頭痛やめまい等の多様な症状を訴える方がいらっしゃるものと認識しております。そうした中、事業者や業界団体においては、香料成分表示などの情報提供や、香りに関する注意喚起を製品の品質表示自主基準に盛り込むなどの取組みを行っていることも承知しています。一方、いわゆる「香害」を含む「化学物質過敏症」の病態や機序については、未解明な部分が多く、疾患概念や診断基準も確立していないことから、現時点でいわゆる香害の観点から表示事項を定めることは困難と考えておりますが、関係省庁や業界とも連携しながら、科学的知見や今後の社会動向等を踏まえ、必要な対応について検討を進めることが重要だと考えます。 |
| 日本維新の会 | ①はい |
| 日本共産党 | ①はい |
| 国民民主党 | ④その他 縦割り行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。 |
| 社会民主党 | ①はい |
| れいわ新選組 | ①はい |
| 参政党 | ①はい |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問15)敵基地攻撃能力の保有について、どのようにお考えですか。以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①戦争放棄をうたった平和憲法のもとでは認められない ②憲法9条を専守防衛と説明してきた政府解釈に反するので認められない ③改定安保3文書に記載されているように専守防衛の範囲の能力を持つことだから問題ない ④日本国憲法との齟齬があることは事実なので、憲法を改正して、憲法9条を専守防衛と解釈せずに、安保3文書でも敵基地攻撃能力保有と明記すべき ⑤その他 |
| 自由民主党 | ③改定安保三文書に記載されているように専守防衛の範囲の能力を持つことだから問題ない 相手から武力攻撃を受けた場合の必要最小限の自衛の措置として行使される「反撃能力」は憲法の精神にのっとったものです。脅威の現実化に対応するには抑止力の向上が不可欠です。 |
| 立憲民主党 | ⑤その他 わが国島しょ部などへの軍事的侵攻を抑止し、排除するためのミサイルの長射程化など、自衛のためのミサイル能力の向上を進めます。他国領域へのミサイル打撃力の保有・行使については、政策的な必要性と合理性を満たし、憲法に基づく専守防衛と適合するものでなければなりません。 |
| 公明党 | ③改定安保3文書に記載されているように専守防衛の範囲の能力を持つことだから問題ない |
| 日本維新の会 | ⑤その他 今後さらに議論していきたい。ロシアのウクライナ侵攻後、安全保障体制が揺らいでおり、他国からの侵略やテロに対抗するため、積極防衛能力については抑止力を高める観点から必要性について議論してゆく。 |
| 日本共産党 | ①戦争放棄をうたった平和憲法の下では認められない ②憲法9条を専守防衛と説明してきた政府解釈に反するので認められない |
| 国民民主党 | ⑤その他 ロシアによるウクライナ侵略により国際秩序が根底から覆される危機にさらされる中、中国の急速な軍備拡大、頻繁な領海侵犯、北朝鮮による我が国周辺への度重なるミサイル発射やロシアによる北方領土への新型ミサイル配備等、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。このような厳しい安全保障環境を踏まえつつ、「戦争を始めさせない抑止力」の強化と、「自衛のための打撃力(反撃力)」を保持します。激変する安全保障環境に対応するため、日米安保体制をさらに安定的に強固なものにしていくことは、日本の安全のみならず、アジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠です。日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を堅持・強化しつつも、米国に過度に依存し過ぎている日本の防衛体制を見直し、「自分の国は自分で守る」ことを安全保障政策の基本に据え、必要な取り組みを行います。 |
| 社会民主党 | ①戦争放棄をうたった平和憲法のもとでは認められない |
| れいわ新選組 | ①戦争放棄をうたった平和憲法のもとでは認められない ②憲法9条を専守防衛と説明してきた政府解釈に反するので認められない |
| 参政党 | ⑤その他 敵基地攻撃能力の保有については必要と考えます。憲法については国民により新たに憲法をつくる「創憲」を提案しています |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問16)防衛費を5年間で43兆円、GDP2%に拡大することについて、どのようにお考えですか。以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①そもそも軍隊のないはずの日本で防衛費は必要ない ②これまでの政府解釈である専守防衛に必要な最低限に抑えるべき ③第二次安倍政権より前の水準を維持すべき ④世界的なテロ行為の増大、覇権国家の脅威が増している中で拡大は当然である ⑤東アジアの力の均衡、日米軍事同盟における日本の役割からして妥当である ⑥GDP2%は国際水準からしても低い。もっと上げるべき ⑦その他 |
| 自由民主党 | ⑤東アジアの力の均衡、日米軍事同盟における日本の役割からして妥当である 東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、わが国を守り抜くために必要な防衛力の抜本的強化は不可欠です。43兆円・GDP2%はその基盤です。 |
| 立憲民主党 | ⑦その他 防衛力の強化や真に必要な防衛予算の一定の増額は理解しますが、令和5年から5年間で2倍、GDP比2%という総額ありきの急激な予算増は無駄や不正の温床になりかねません。増額に伴う防衛増税が先送りされており財源確保のめども示されていませんが、増額と財源はセットで国民に提示すべきです。防衛増税は行いません。 |
| 公明党 | ⑤東アジアの力の均衡、日米軍事同盟における日本の役割からして妥当である |
| 日本維新の会 | ④世界的なテロ行為の増大、覇権国家の脅威が増している中で拡大は当然である |
| 日本共産党 | ②これまでの政府解釈である専守防衛に必要な最低限に抑えるべき ⑦その他 大軍拡は直ちに中止すべきです。国民の安全と暮らしを犠牲にするのではなく、軍事費を減らし、社会保障や教育など暮らしを応援する予算に振り向けるべきです。憲法9条を生かした外交に全力で取り組み、紛争を戦争にしない、平和な東アジアをつくることをめざします。 |
| 国民民主党 | ⑦その他 従来領域(陸、海、空)において不十分であった継戦能力の確保や抗堪性の強化を抜本的に見直して整備するほか、防衛技術の進歩、宇宙・サイバー・電磁波等の新たな領域に対処できるよう専守防衛に徹しつつ防衛力を強化するため、増税に頼ることなく必要な防衛費を増額します。 |
| 社会民主党 | ②これまでの政府解釈である専守防衛に必要な最低限に抑えるべき |
| れいわ新選組 | ②これまでの政府解釈である専守防衛に必要な最低限に抑えるべき |
| 参政党 | ④世界的なテロ行為の増大、覇権国家の脅威が増している中で拡大は当然である |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |
| (質問17)「能動的サイバー防御」法案が5月に可決・成立しました。このことについて、どのようにお考えですか。以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。 ①国益を損なうサイバー空間への攻撃は、事前に察知し、無力化を図る必要がある ②日常における国内外のサイバー空間の監視活動は、国益を守るためには必要である ③収集対象となるのは海外通信に限られ、メール内容は見ないので通信の秘密は守られる ④憲法9条の戦争放棄、憲法21条の通信の秘密を侵害する可能性があるので反対 ⑤情報収集は、第三者機関の事前承認を義務付けても例外を認めており、歯止めにならない ⑥戦争につながるサイバー攻撃の無力化は認めないが、監視活動は認める ⑦その他 |
| 自由民主党 | ①国益を損なうサイバー空間への攻撃は、事前に察知し、無力化を図る必要がある 被害が瞬時かつ広範に拡散するというサイバー攻撃の特性を踏まえ、攻撃の未然防止や被害拡大防止のため、被害発生のおそれを認知し次第、被害防止措置をとれる権限整備が必要です。 |
| 立憲民主党 | ⑦その他 国会による監視機能を強め、国民の権利を不当に侵害しないか、国際法に違反しないか等の観点から監視していく。 |
| 公明党 | ⑦その他 近年、巧妙化・深刻化するサイバー攻撃の脅威が増しており、政府機関や企業への被害が後を絶ちません。こうした中で、被害を未然に防ぐための能動的サイバー防御が重要となります。政府が主に防御対象とするのは、サイバー攻撃の99%以上を占める海外からの発信です。官民連携を強化し、防御策の実効性を高めることが求められます。しかし、政府による通信情報の分析と、憲法で保障される「通信の秘密」やプライバシー保護との両立が課題です。能動的サイバー防御法では、政府が防御措置を行う際に「サイバー通信情報管理委員会」の事前承認を原則とするなど、政府の権限が必要以上に拡大しない仕組みを盛り込んでいます。とはいえ、プライバシー侵害や政府による情報漏洩への懸念を解消するため、政府はサイバー防御の必要性と「通信の秘密」を守る取り組みを丁寧に説明し、国民への理解を深める努力を続けるべきです。 |
| 日本維新の会 | ①国益を損なうサイバー空間への攻撃は、事前に察知し、無力化を図る必要がある ②日常における国内外のサイバー空間の監視活動は、国益を守るためには必要である |
| 日本共産党 | ④憲法9条の戦争放棄、憲法21条の通信の秘密を侵害する可能性があるので反対 |
| 国民民主党 | ⑦その他 サイバー安全保障を確保するために、我が国においても平時の段階からサイバー攻撃者の動向を探り、対処を行う能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)について、能力整備と実施体制の整備を行うとともに、「サイバー安全保障基本法(仮称)」を制定します。情報収集衛星を質・量ともにレベルアップを図るとともに、イギリスのJIC※等を参考にしつつ、日本のインテリジェンス能力を高めます。安全保障上の観点から、公共インフラやカーナビ情報等の実情について調査し、所要の対策を講じます。 |
| 社会民主党 | ④憲法9条の戦争放棄、憲法21条の通信の秘密を侵害する可能性があるので反対 |
| れいわ新選組 | ④憲法9条の戦争放棄、憲法21条の通信の秘密を侵害する可能性があるので反対 ⑤情報収集は、第三者機関の事前承認を義務付けても例外を認めており、歯止めにならない |
| 参政党 | ①国益を損なうサイバー空間への攻撃は、事前に察知し、無力化を図る必要がある |
| NHK党 | 無回答 |
| 日本保守党 | 無回答 |