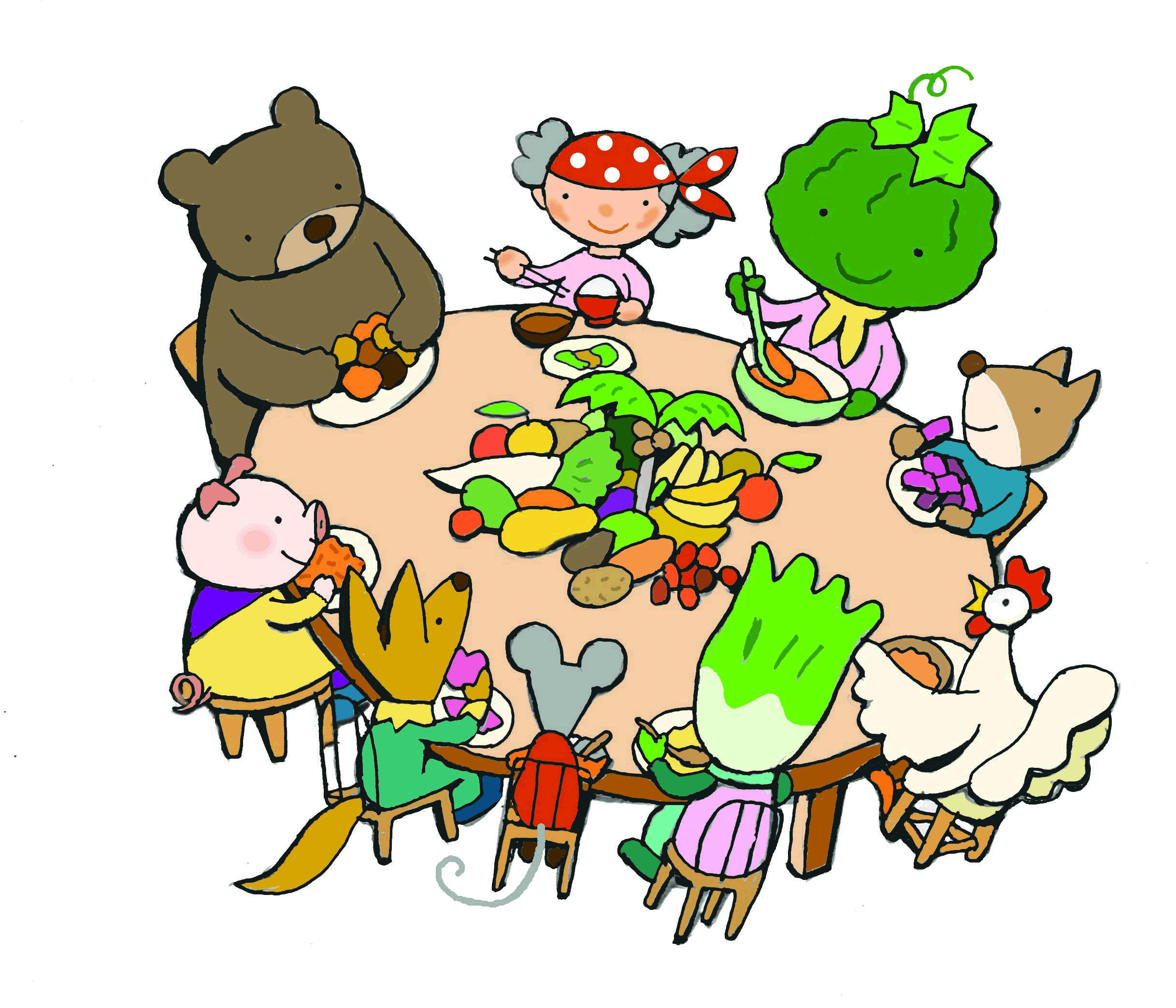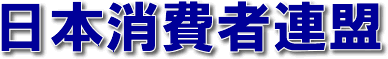野菜の高騰が止まらない。農村部を控えた地方都市でも、スーパーをのぞくと白菜4分のひと切れで170円という値段がついていた。それではと農協の直売所をのぞくと、小ぶりだったり色が悪かったり傷があったりと、さすがに農協らしく一生懸命集めた気配が感じられたが、普段よりは高い。
テレビをつけると、取材を受けた安売り八百屋のおじさんが、当分安くはならないねと断言していた。野菜高騰の原因は、このところ続く天候異変にあるというのが定説だが、どうもそれだけではないという気がしてならない。需要、供給双方に、構造的な異変が起きているのではないか。
供給サイドでいえるのは、生産力の減退だ。ごく少数の品目を大量に作る産地では、もうだいぶ前から外国人労働者に頼らざるを得なくなっている。建設業やサービス業で人手不足が深刻化する中で、外国人労働者も農業には回らなくなった。大量生産、大量販売、大量消費というシステムが機能不全に陥ったのである。
加えて産直や直売、町の飲食店や八百屋さんなどの小さな消費を支えていた小さな生産も、高齢化のいっそうの進展で生産からの撤退が急速に進んでいる。村の空家や耕作放棄地の激増がそのことの深刻さをあらわしている。つまるところ、食の再生産の仕組みそのものが壊れる寸前まで来ているのだ。
需要の側はどうか。いまスーパーの野菜売り場では、カット野菜の棚が大きくなっている。それだけ手間暇かけずに調理できるニーズが増えているのだ。日本の野菜生産はロボットが活躍する野菜工場が担う時代に入りつつあるのではないか。さてどうするか。この先を考えるのも消費者運動の課題だろう。
(大野和興)